死別直後、
悲しみと同時に今後の生活に対する大きな不安に押しつぶされそうになりました。
これからの生活がどうなってしまうのか想像がつかず、
ネットで調べても情報も少なく、
同じ経験をした人も周囲におらず、不安は膨らむばかり…
そんな死別直後の私と似た状況にいる方の参考になればと、
- 我が家の生活費や遺族年金
- ひとり親家庭が受けられるサポート
- お金の不安を軽減する方法
についてまとめました。
Contents
リアルな収入公開〜我が家の遺族年金額〜
死別の苦しみの上にズッシリのしかかってくる「お金の不安」。

「遺族年金」と検索してもムズカシイ計算式ばっかり出てきてよくわからない…
結局いくらもらえるの?!
死別直後、調べてもよく分からずやきもきしたので、ひとまず具体的な金額を公開します。
※家庭により異なるため、あくまで我が家の場合です。
我が家の遺族年金の金額を公開
我が家の前提条件:子供2人、夫は元公務員(国民年金・厚生年金共に加入していた)
◆遺族年金:月額 約140,000円
◆児童手当:月額 20,000円(3歳未満:15,000円/以降高校卒業まで:10,000円)
上記が、子供が18歳になるまでの収入(予定)です。
(子供が18歳になると子の加算額がなくなるため、遺族年金が下がります。)

遺族年金は2ヶ月おきに、2ヶ月分まとめて、
児童手当は6月・10月・2月に前月分までをまとめて振り込まれます。
遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があり、
受給要件を満たしていれば両方を受給できます。
ざっくり言うと下記のようなイメージです。
遺族基礎年金:国民年金加入者の子のある配偶者・子が受給できる
遺族厚生年金:厚生年金加入者の家族が受給できる
遺族年金を受給するには、年金事務所での手続き(事前予約必須)が必要です。
遺族基礎年金いくらもらえる?一覧表
遺族基礎年金は受給金額が一律で決まっています。
受給金額に個人差がある遺族厚生年金は一旦置いておいて、
遺族基礎年金を家族構成ごとに計算すると、受け取れる金額は下記の表の額になります。
| 家族構成 | 基礎年金額 | 子の加算額 | 児童手当 | 合計年額 | 月額 |
| 子供1人 | 816,000円 | 234,800円 | 120,000円 | 1,170,800円 | 97,566円 |
| 子供2人 | 816,000円 | 469,600円 | 240,000円 | 1,525,600円 | 127,133円 |
| 子供3人 | 816,000円 | 547,900円 | 360,000円 ※ | 1,723,900円 | 143,658円 |
| 子供4人 | 816,000円 | 626,200円 | 480,000円 ※ | 1,922,200円 | 160,183円 |
*受給要件を満たしている場合の金額です。
遺族基礎年金の受給要件(遺族年金ガイドより)
遺族基礎年金は下記のいずれかに当てはまっている場合、「子のある配偶者」または「子」が受給要件を満たします。
① 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
② 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有し
ていた方が死亡したとき。
③ 老齢基礎年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間およ
び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る) が死亡したとき。
④ 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年
以上ある方が死亡したとき。
※①②の場合、
・国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期
間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。
【納付特例】
死亡日が令和8年3月末日までにあるときは、次のすべての条件に該当する場合、
納付要件を満たすものとされています。
・死亡日において、65歳未満であること
・死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料
の未納期間がないこと
*遺族基礎年金は子供がいない場合は支給されません。(妊娠中に死別した場合は受け取れます。)
*子供は3歳以上高校生以下と仮定。子の加算額は18歳になった年度の3月末まで。
※3人目以降の子は3歳〜小学生までの児童手当は月額3万円ですが、ひとまず1万円として計算しています。

これだけで十分に生活できるほどの金額ではありませんが、
「天国からも養ってくれてありがとう」と思います。
上の遺族基礎年金の表の金額に加えて、
厚生年金に加入していて受給要件を満たす場合は、
加入期間や金額に応じて、年金額が上乗せされて支給されます。
*遺族厚生年金は子供がいなくても受け取れますが、死別時に30歳未満の方は5年間のみの支給です。
遺族年金についてより詳しく知りたい方は日本年金機構のサイトを、
児童手当について詳しく知りたい方はこども家庭庁のサイトをご確認ください。
ひとり親家庭への補助金「児童扶養手当」はもらえない
遺族年金の月額が、児童扶養手当の月額を超える場合は支給対象となりません。
児童扶養手当は収入により金額が決まります。
全額支給される場合の金額は(自治体にもよりますが)下記の通り。
| 対象児童数 | 全部支給 |
| 1人 | 45,500円 |
| 2人 | 56,250円 |
| 3人 | 62,700円 |
| 4人 | 69,150円 |
遺族年金が上記の金額を下回る場合のみ、差額が支給されます。
遺族年金は、基本的にはこの金額を上回ると思うので、児童扶養手当はもらえない方が多いと思います。

死別直後、若年死別という地獄の中で育児するんだから
遺族年金も児童扶養手当も両方くれ〜って
思っちゃったのは私だけじゃないはず😂
児童手当について詳しく知りたい方はこども家庭庁のサイトをご確認ください。
ひとり親が利用できる制度をご紹介
ひとり親家庭の医療費助成制度
ひとり親家庭の医療費助成制度とは、ざっくり言うと…
◆子供も親も通院・入院時にかかる医療費・薬代の自己負担が500円〜1割負担で済む
(自治体や、住民税非課税世帯か課税世帯かにより負担額が異なります。)
といった制度です。
通院・入院してもほとんどお金がかからないのは非常にありがたいです。
ただし、自分で手続きをしなければ助成は受けられません。

戸籍謄本などの書類が必要で
役所で手続きしないといけないのが面倒ですが、
早めに手続きを済ませてしまいましょう…!
※以下の表の金額以上の所得を得ている場合は制度を利用できません。
(所得金額に遺族年金は含みません。自治体により金額は異なります。)
| 子供の人数 | ひとり親の所得 |
| 1人 | 230万円 |
| 2人 | 268万円 |
| 3人 | 306万円 |
| 4人以上 | 1人増えるごとに38万円加算 |
詳しくはお住まいの自治体のサイトをご確認ください。
児童育成手当
児童育成手当は、ひとり親に支給される手当です。
- 一部の自治体にしかない制度
- 遺族年金と併用できない場合もある
- 所得制限がある
など、受け取れない場合もありますが、
受給対象であれば子供1人につき、13,500円支給されます。
詳しくは「児童育成手当+お住まいの地域名」で検索してみてください。
ひとり親家庭の住宅手当
条件に該当すれば、月額5千円〜1.5万円の住宅補助が受けられます。
- 一部の自治体にしかない制度
- 所得制限などの支給条件がある
詳しくは「ひとり親家庭 住宅手当+お住まいの地域名」で検索してみてください。
非課税世帯の優遇措置
ひとり親の住民税非課税世帯の条件は、
前年の合計所得金額が135万円以下の方
(給与所得者の場合年収204万4000円未満)
です。
※子供の数や自治体により異なります。
※この金額に遺族年金は含まれません。
非課税世帯の優遇措置としては、以下のようなものがあります。
◆住民税・所得税がかからない
◆保育料が0歳から無償化
課税世帯は3歳〜5歳のみ無償ですが、
非課税世帯は0歳〜5歳まで保育料がかかりません。
◆大学や専門学校の授業料減免
学費の減免・給付型奨学金の支給が受けられます。(詳しくはこちら)
◆国民年金保険料の免除・納付猶予
ただし、支払う年金額が下がると、将来受け取れる年金額が少なくなるため
個人的には可能な限り支払う方が良いと考えています。
◆国民健康保険料の減免
国民健康保険料は所得に応じて金額が変わるため、
非課税世帯は保険料が軽減されます。
その他のサポート
- こども家庭庁シングルマザー・シングルファザーの暮らし応援サイト
ひとり親家庭が受けられる支援についてまとめられたサイトです。 - こども食堂ネットワーク
子供が一人でも行けて、無料または低額で利用できる地域の食堂です。
(このサイトに載っていないこども食堂もたくさんあります) - あしなが育英会
病気や災害、自死などで親を亡くした子どもたちや、障がいなどで
親が働けない家庭の子どもたちを奨学金、教育支援、心のケアで支える民間非営利団体です。
- エミナル
死別ひとり親という同じ境遇の方と交流できるコミュニティです。
お金の不安を軽減するために
【参考情報】我が家のリアルな家計事情
◆遺族年金(14万円)+児童手当(2万円)→月額約16万円(子供2人)
◆住民税非課税の範囲内で、心身の負荷が少ない働き方→月収11万円程度
◆合計で月収約27万円、年収約324万円(非課税なのでこの金額が手取り)
◆実家や公営住宅に住んで固定費を下げる(公営住宅なら家賃3万円程度)
◆ひとり親家庭等医療費助成制度で医療費はほぼかからない
◆非課税世帯なので保育料や学費は無償・減免が利用できる
というのが我が家のリアルな家計事情です。

お金のライフプランを作成した結果から見ても、
贅沢をしなければ、不安なく生活していけます。
※ただし、死別後1年間やストレスが大きかった時期は
散財しまくって思いっきり赤字生活でした!
時間をかけてストレスの少ない暮らし方・働き方を見つけて、
ようやく生活が落ち着いてきました。
将来に備えるため、NISAもしながら、
当面の間は非課税世帯の範囲内で、負担の少ない働き方を続ける予定です。
(心身ともにゆとりの持てる生活が整ってきたことで
「もっと仕事も頑張ろう」という気力も徐々に湧いてきています!)
急に死別してひとり親になっても、生活費はなんとかなる
死別してシングルになってしまった場合、
それまで通りの暮らしは出来なくても、様々な制度を利用することで
生活が破綻するほどの事態に陥ることは多くないと思います。
とはいえ、子供が成人すれば遺族年金はガクッと減りますし、
色々な状況は家庭により異なります。
- 実家や義理実家のサポートの有無
- 住居に家賃がかかるのか
- 子供の年齢
- 仕事
- 貯金額
- 保険金、相続財産
- 借金、ローン返済 etc.

◆学費や老後資金はいくら必要か・どう準備するか
◆余剰資金はどのように管理・運用するか
◆いざという時の備え・保険は十分か
など…
ひとり親だからこその不安がありますよね。
ひとり親だと、お金のことを相談できる相手もいないし、
不安を一人で抱えている方も多いと思います。
でも、必要以上に不安を感じて、
「必死に働かなきゃ、でも心身が辛い…」という状況にいる方もいらっしゃるかもしれません。
お金の不安は早めに解消するのがおすすめ
死別の絶望・苦しみにまみれた日々から少しでも早く抜け出したい方は、
一つでも多く、ストレスの元を解消するのがおすすめです。
なぜなら、
心の負荷が大きいほど、苦しみが長引くからです。

死別して悲しい、苦しい。
仕事に行くのもしんどい。
お金のことも不安。
何もかも投げ出したい…。
私は死別してから長い間、そう思っていましたが、
お金のプロに相談して、今後のお金について相談したことで
経済状況が可視化され、漠然としたお金の不安がなくなり、
ストレスが軽減されて、将来に対する絶望感が和らぎました。
お金の不安を少しでも感じている方は、
お金の専門家であるFPさんに相談してみることもおすすめです。
まとめ
この記事で最も伝えたいことは、
◆死別シングルになっても生活費はなんとかなる
◆心身を削りながら無理をしてたくさん働くより、
社会や周囲に頼りながら
まずは心を回復させることを優先するという方法もある
(その方が早く自分らしさを取り戻せると思います)
ということでした。
辛い状況にある方が、少しでも穏やかに気を楽に過ごせますように…。
死別経験者の方、よろしければ
コメント欄にどのような生活をされているかシェアいただければ
私も読者さんも参考にさせていただけると思います。
(皆さまもっとしっかりお仕事されてる方が多いんでしょうか…!?)
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
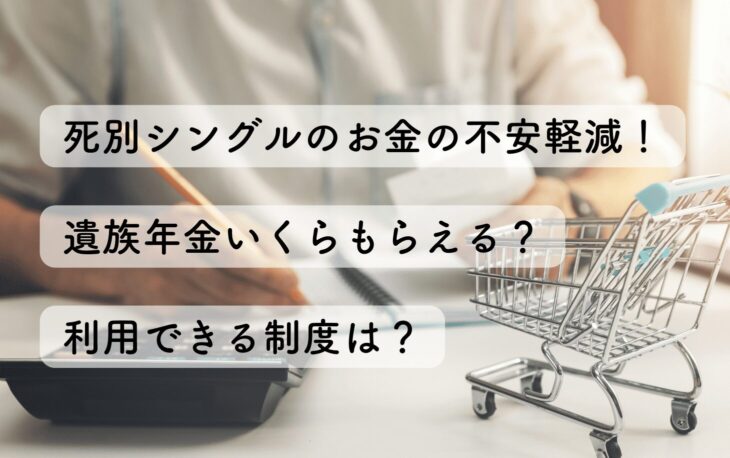

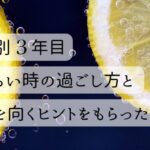


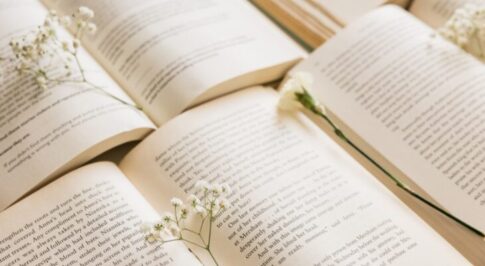

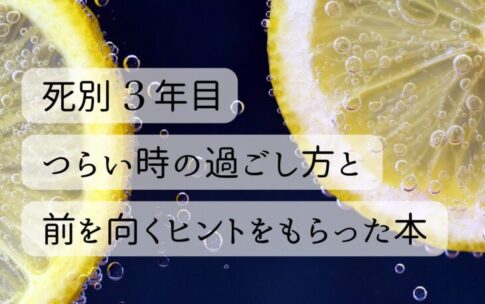
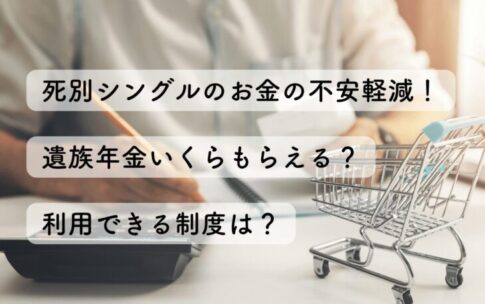
こんにちは。
20代で幼い子供2人を抱えて、最愛の夫と死別を経験しました。